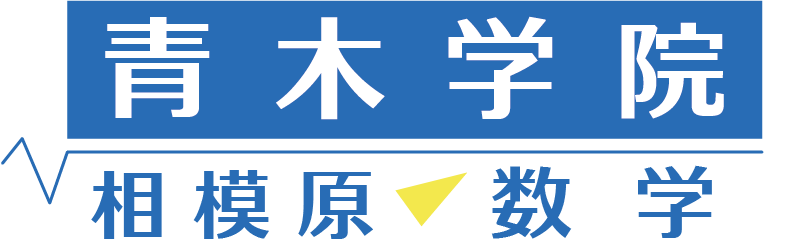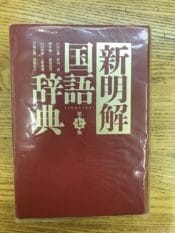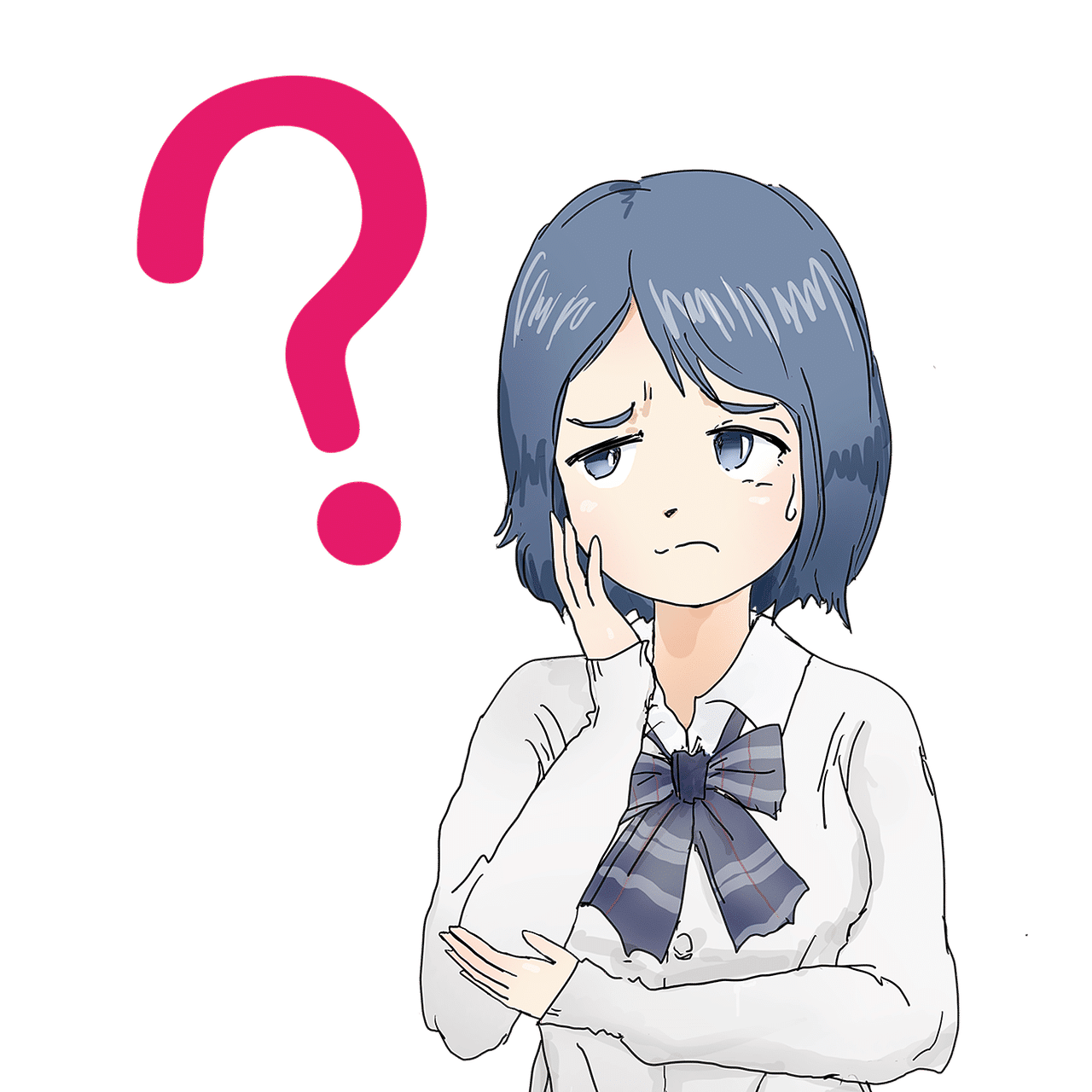やっているように見えて学力が伸びない理由3選

学力が伸びるかどうかは生徒の日常の行動で分かります。
単に学習量が多いか少ないかというラインもあります。
しかし、一見やっているよう見えても学力が伸びない生徒がいます。
それはどういうところに問題があるのでしょうか。
僕がよく見かけるのは以下のようなパターンです。
1.指示されたことだけしか学習しない
指示されたことをやらないのは論外です。
少なくとも指示されたことに従えていないならその場にいる意味が薄れてしまいます。
その上で、指示されたことだけしか行動しないならば意欲が足りません。
テキストを3周しろと言われて3周するだけではダメです。
なぜ3周して何を目指すのかを考えれば、自分のやるべきことが見えてくるはずです。
ただやるのではなく、意味や目的を考えて進化せねばなりません。
2.新しい学習内容の習得意識が低い
学習する分野として新しいことについてもそうです。
しかし、それ以上に細かいアップデートへの意識が足りない生徒は伸びません。
例えば中学2年生の連立方程式では、加減法を学習します。
このときに「加法と減法のどちらで解くのか?」「xとyのどちらを消すのか」という話があります。
これをなんとなくやっていたり、手癖でやっている生徒は安定して90点を超えることがありません。
どういう状況でどの手順で解くと、どういうミスが減らせるのか。
そういうレベルまで身につけようとすれば学力が上がります。
3.学習全体を俯瞰できない
自分が何のために学習しているかを意識しましょう。
目先の問題に◯がつくことを目指してしまうと、行動は雑になります。
◯になることが目当てですので、間違いを見落とす可能性が上がります。
ときには誤答を書き直して◯にしてしまう生徒さえ現れます。
大事なことは「学力を上げる行動を一つずつやる」ことです。
誤答を書き直したとて、賢くも強くもなりません。
できないことが一つできるようになれば、成長です。
成長を重ねれば目標に到達する可能性は上がります。
いまやっていることがどういう未来につながるかを意識しましょう。