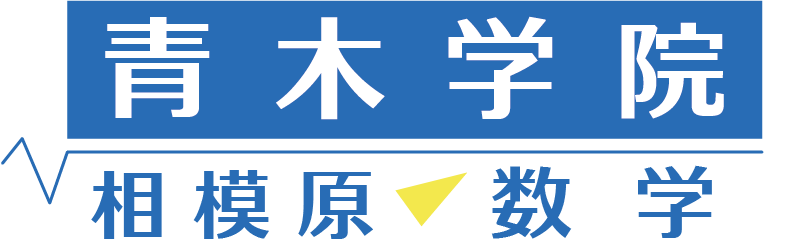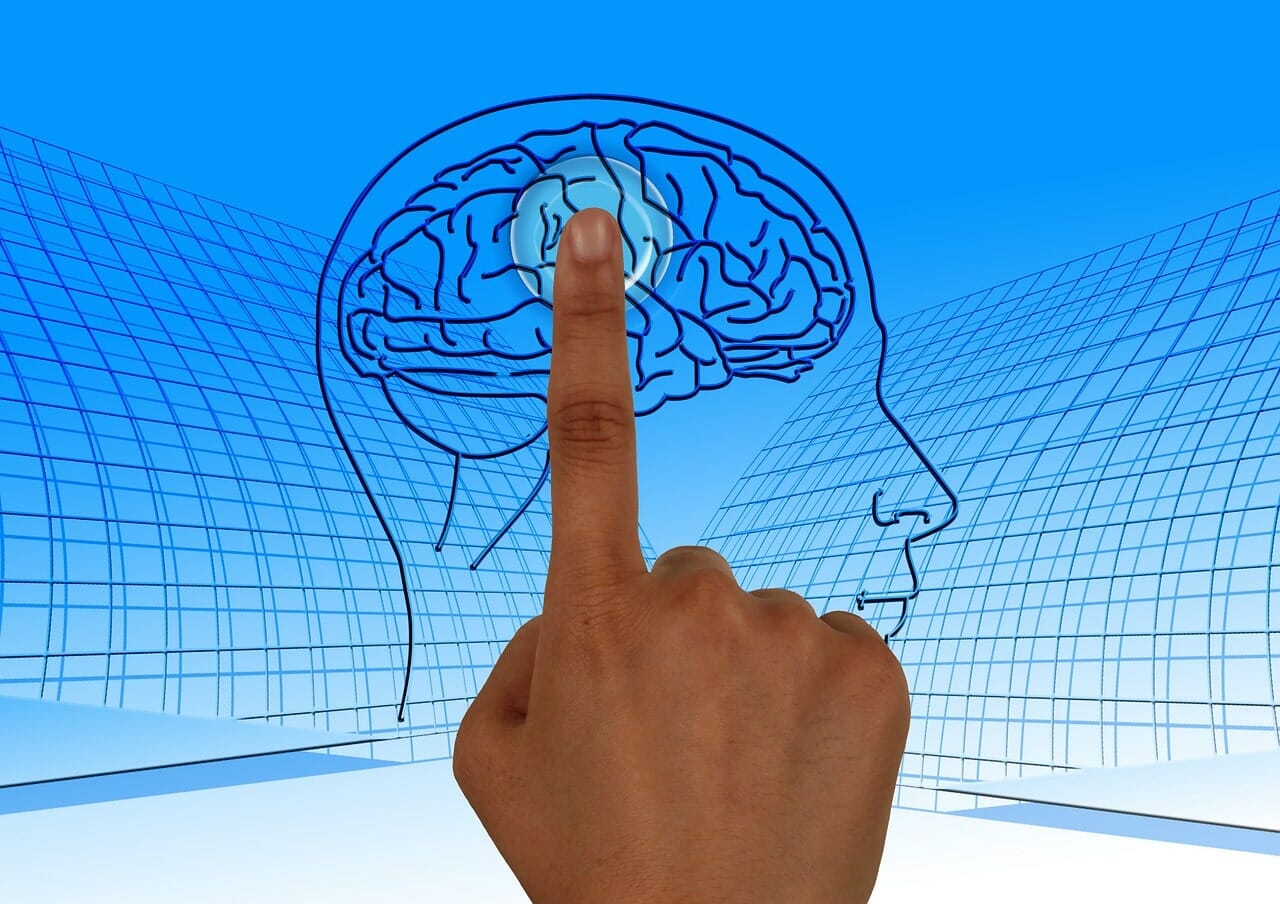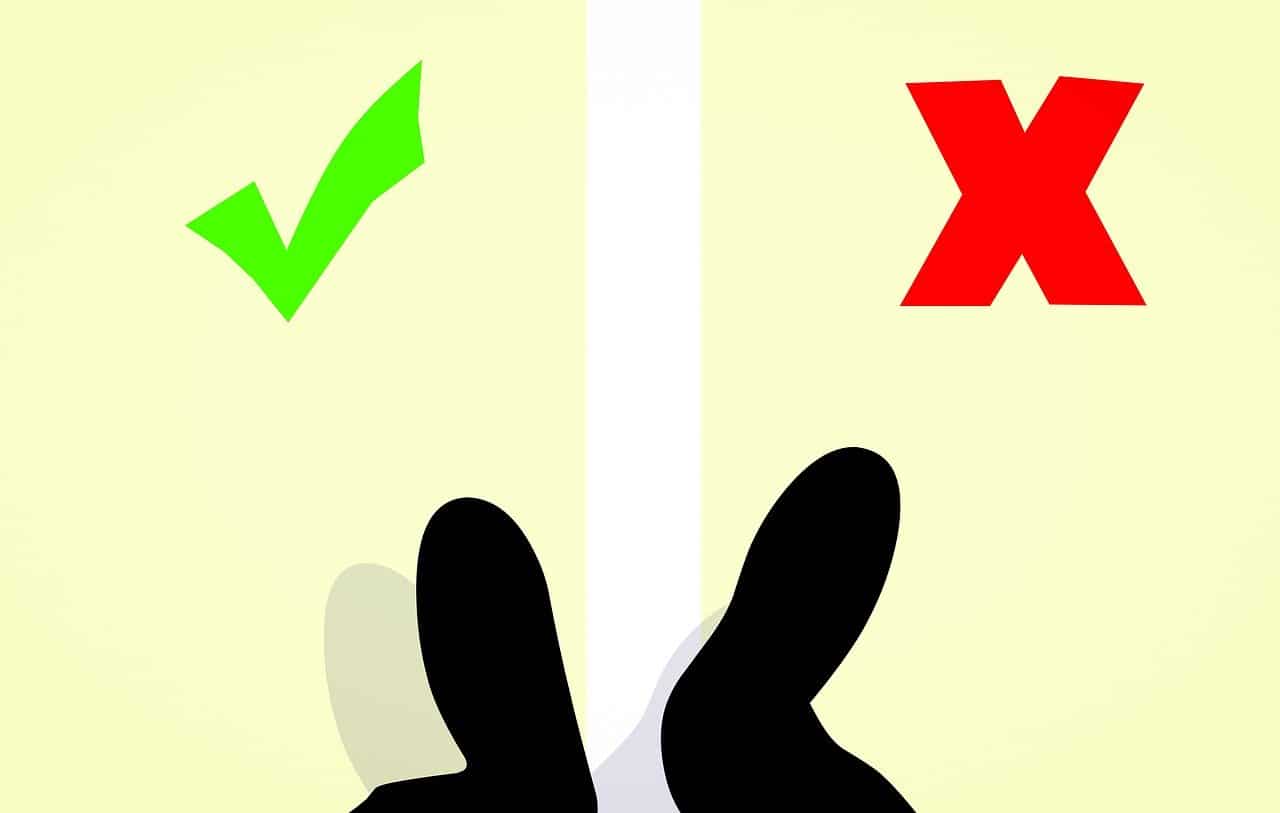「読む」「聞く」ことが最初のインプット

学力が伸びる人間は学習の基本動作ができています。
結局「読む」「聞く」ができているかインプットを大きく左右します。
これは新規の学習内容をインプットするときだけではありません。
問題文の条件を読んで答えるという基本動作もまた、ミニインプットです。
「thatを使って」「この順番で」「kmで」などの条件をイメージしています。
仮に文法的・数学的に正しいことをやっていても、ここを逃せば減点です。
「そんなことを見落とすなんて」と思うお母さんも多いでしょう。
しかし、偏差値55未満の生徒の大半は見落とします。
英語にもう少し寄せて言えば「時制」「肯定否定疑問」の種別なども見落とします。
極めて雑に流れで問題と向き合う習性がついているからです。
このインプットレベルの低さの原因の一つは音読の不足にあります。
漢字も助詞も含めてごまかさないで読む習慣がついているかどうかです。
文字を読むことを面倒だと思うようになれば、学力は絶対に伸びません。
言葉・文字を軽視する人間がインプットを充実させることは不可能だからです。
書いてあることをそのまま読み通すこと。
書かれている内容を考えて自分の行動を決定すること。
こういう当たり前のインプットレベルが精度高くやれれば、学力は伸びます。
これは会話でも同様です。
言われているとおりに聞き取ること。
それをオウム返しできること。
ここができない雑な聞き方では、インプットが落ちます。
人の話を雑に聞いているならば、学校の授業を有効活用できないからです。
松江塾真島先生が仰るところの「人の話は目で聞く」気合が必要です。
そのためにも、お母さんが日頃から子供から子供と目を合わせて会話することから始めましょう。
僕の下から県立相模原高校に進学していった生徒たちは例外なくここが出来ていますからね。