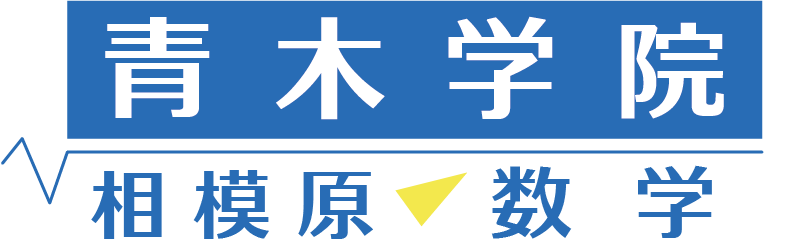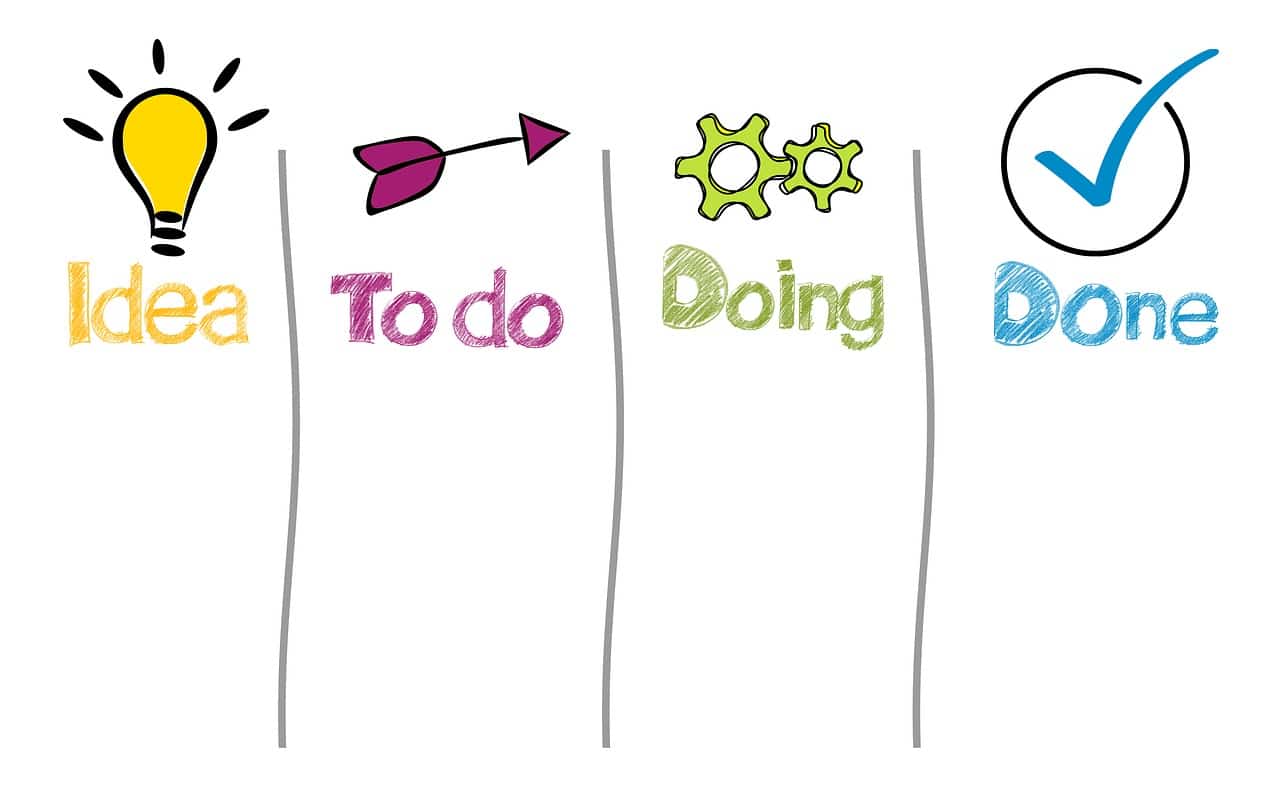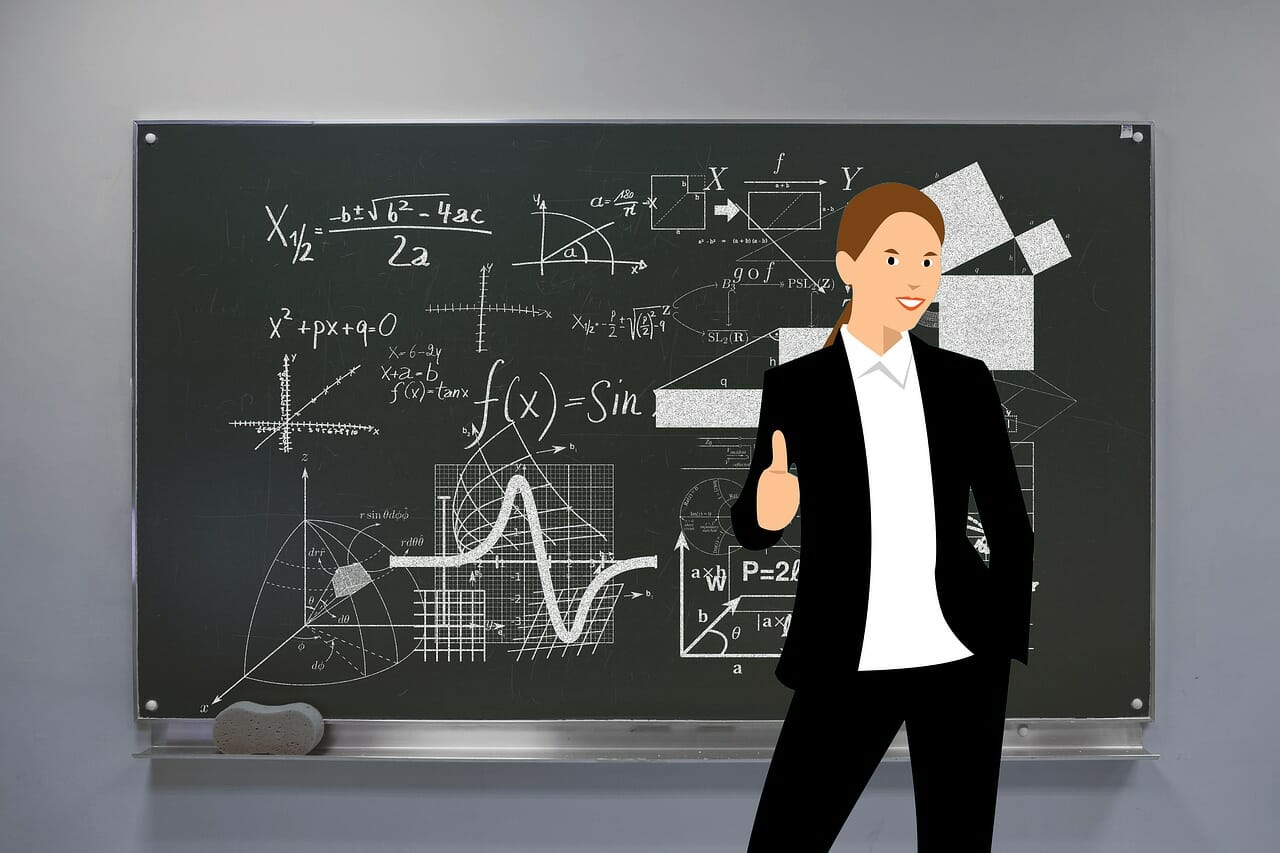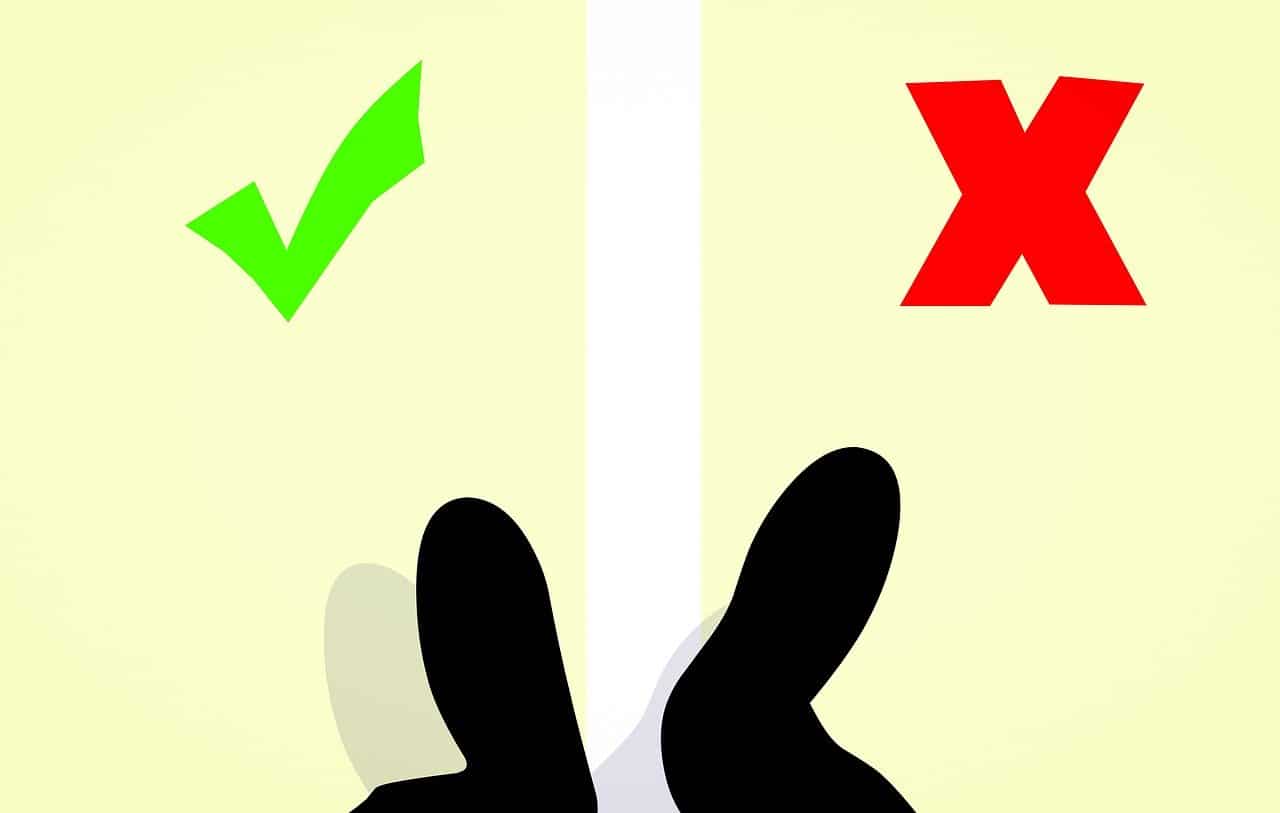ルールを守る生活が子供の学力を伸ばす
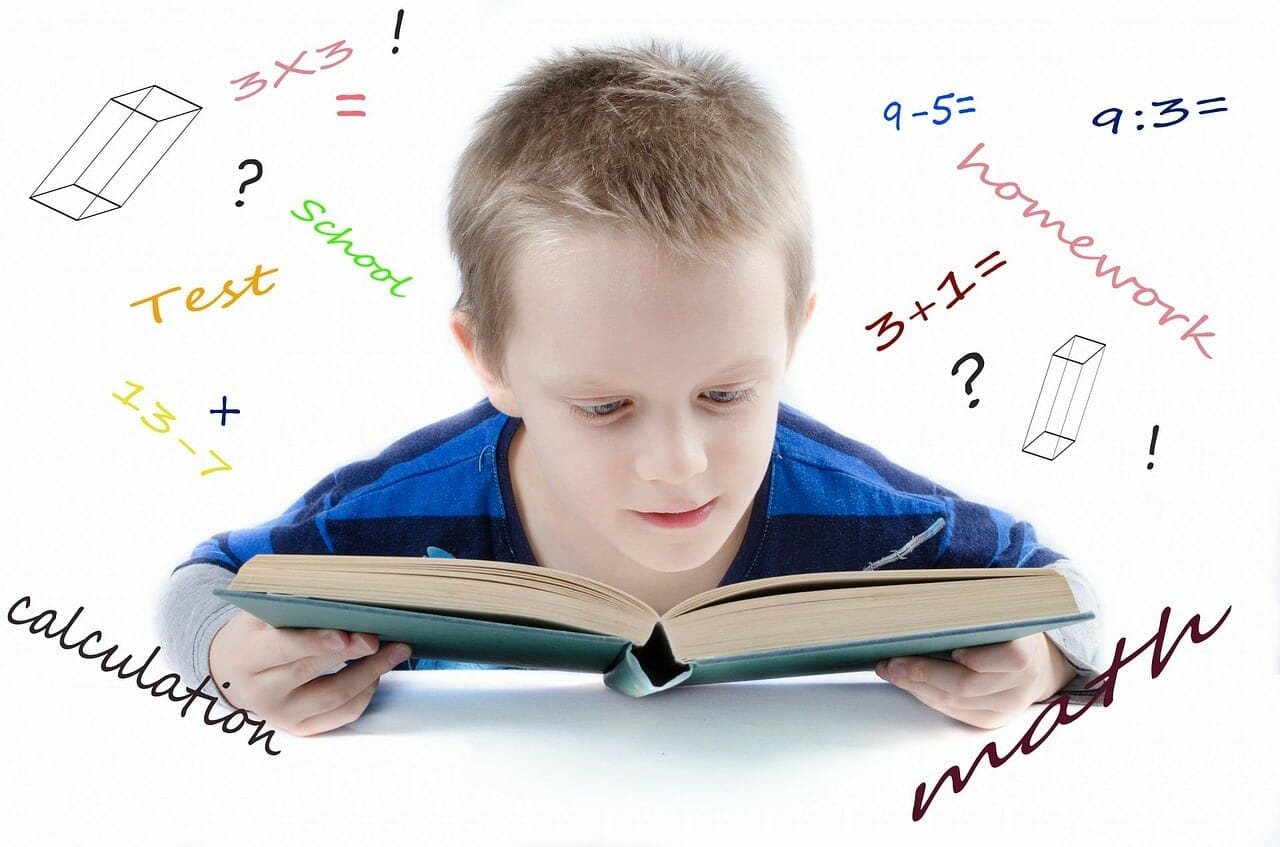
相模原市の学習塾・数学特訓青木学院です。
塾には合格を求めて通う人がほとんどのはずです。
合格するというのは合格点が取れているということです。
合格点を取るためには賢くなる必要があります。
ここで言う賢さを理解しているかどうかは、日常から学力を磨けるかどうかに関わります。
賢さの一つとしてあるのが「いかにルールを守れるか」ということがあります。
ルールを守れる生徒は学力が伸びますし、その逆もまた然りです。
今日はルールを守れるというのはどこから来る行動かを考えてみましょう。
明文化されていないルールから
ルールを守るためにはまずルールを知ることです。
明文化されていないが、誰もが守ることを前提としているレベルもあります。
「聞かれたとおりに答える」というのがその最たるものでしょう。
意味がなんとなく通じるからいいじゃないか、という雑なコミュニケーションをしていてはダメです。
「どういうことか」「どういう感情か」「何故か」
このあたりのフォーマットを守ることさえできていないなら、ルールに対する意識が低いです。
問題を解くときの行動もルールだ
解き方のルールも大事です。
未知数を文字で置く。
方程式の係数はなるべく整数に近づける。
符号の確認はペン先で行う。
単位の確認は初期に行う。
手が止まる場合には図と具体例を書く。
そういう習慣としてのルールをどれだけ守れるかはミスを減らし速度を上げるものです。
解き方がルールを守れずブレるうちは、演習も意識も足りていません。
そのレベルでは定期テストで90点を取ること、通知表で5を取ることは難しいです。
ルールに従うのは自由でもある
ルールを守るとは、何も考えずに唯々諾々と従うことを意味するわけでではありません。
ルールを身につけ、その範囲の中で柔軟な発想をすることまでを含みます。
どんなスポーツでも名選手や名チームがルールを無視してプレイすることはありません。
ルールの範囲内で新しい戦術やプレイが生まれます。
それまでより良いプレイは、必ずルールを熟知するところから発達します。
入学試験でルールを破れば、その時点で不合格の可能性さえあります。
そのようなことさえ、本番だけ気をつければなんとかなるというものではありません。
日常からルールを覚え、ルールを守り、ルールを活用して生活することです。
いちいちルールを破ってロスをしていれば効率も落ちます。
そのつまづきが学習への集中力を削げば、なおのこと効率は下がる一方です。
ルールを守ることは効率を上げることでもあるのです。