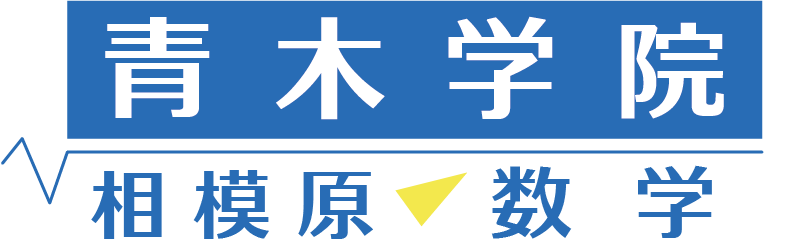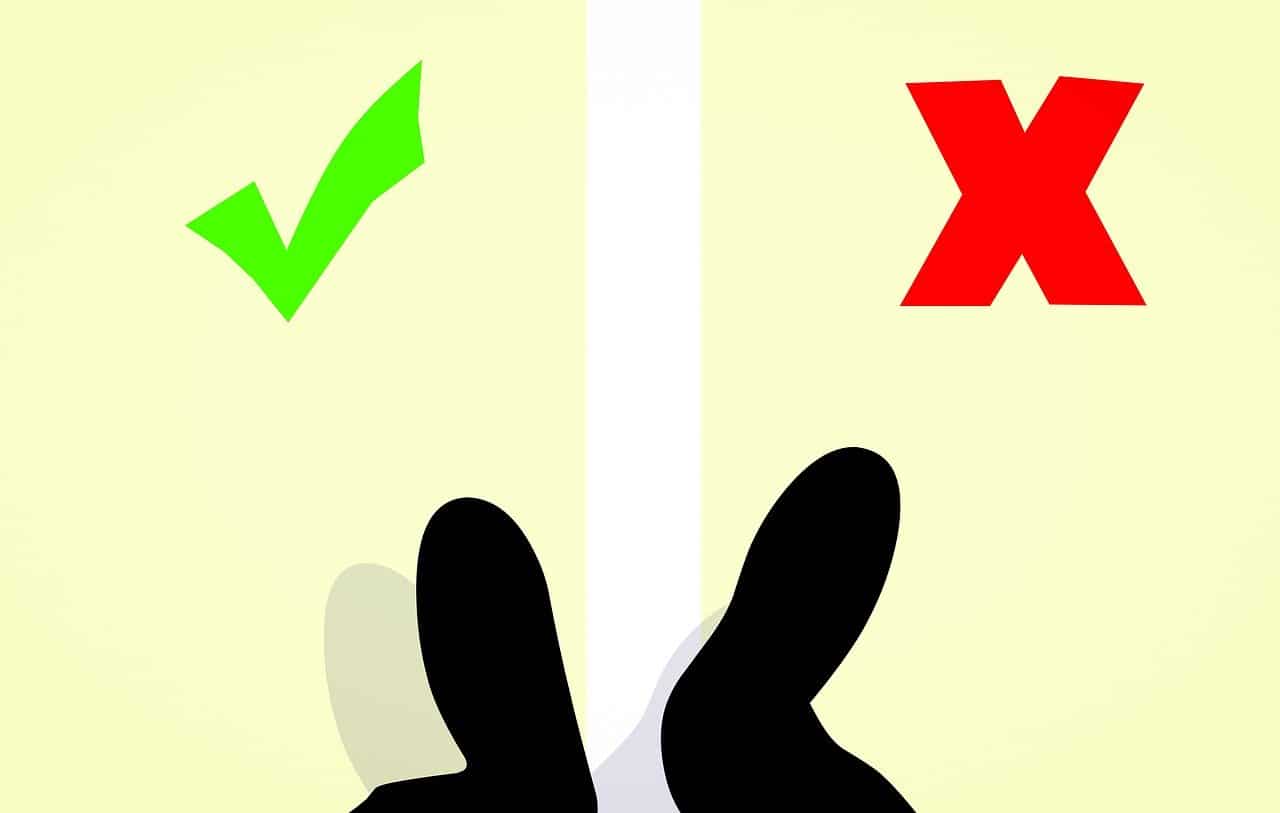県立相模原高校の生徒が数学で脱落する3つの理由

相模原市の学習塾・数学特訓青木学院です。
なぜ県立相模原高校に合格する生徒でも、高校数学に負けていくのでしょうか。
その要因はもちろん一つではないでしょう。
それでも、共通するポイントが3つあります。
1.高校数学の学習量が多くなる
数学に限った話ではありませんが、高校での各教科の学習量は中学よりも増えます。
難度も当然上がっています。
質量ともに増えた高校での学習についていくためには、中学と同様の学習ではいけません。
質を確保した学習を十分な量で行わなければ、高校の看板に負けた大学に進学することになります。
上位高校のほうが定期テストも難しくなるのは道理です。
高校の入学試験は、各高校に合った最低限度の学力があるかどうかを見極めるものでもあります。
ともあれ、その学習量が全教科増えた中で特に抽象度が上がる数学に負けてしまうのです。
2.中学数学と同じ方法論で学習して負ける
中学までの数学である程度得点していたのに、高校のテストでガタガタになる生徒がいます。
これは高校での学習を中学までと同じ方法論で扱うからです。
立式や式変形の手順がシンプルな中学数学と同じパターンマッチングで戦おうとしてしまいます。
高校での数学は上述の通り抽象度が上がります。
精度を上げた理解とさらなる計算力向上がなければ、負けます。
雑になんとなくでも取れていた中学までの点数とはレベルが違ってきます。
小学校の算数でやり過ごした生徒が中学数学で躓くのと同じ仕組みです。
これを克服するためには、中学段階から精度を上げて読む練習がおすすめになります。
3.人についていく学習をしている
僕の目から見て、パッと見で分かりにくい差はここでついていると考えます。
中学までの学習で自主性を養っていない、ただ指示されたことをやるだけの生徒がいます。
素直ないい子なんでしょう。
教師側からすれば扱いやすいことでしょう。
県立相模原高校にいる生徒らしいと感じる人も多いでしょう。
しかし、ここにこそ最大の問題があります。
高校受験のときと同じように他者に依存しすぎた学習をすれば、高校ではドロップアウトします。
それは他者依存、指示待ちによって行動が一手一歩遅れてしまうからです。
授業中でも学習中でも、自分のなすべきことを意識できていない時点で出遅れます。
そしてその遅さは、上位大学への進学に向けては大きな差を生んでしまいます。
とりわけ速度が物を言う数学については顕著です。
手取り足取りの指導を受けた結果として県相生になるわけですが、それこそが致命傷なのです。